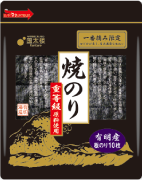| 1990年 |
- アバンス貿易株式会社設立(貿易部門分離独立)・全漁連入札権取得・コーヒー焙煎工場落成
- レギュラーコーヒー/アフターブレンド製法確立
- 世界初コーヒー豆を産地・等級別に焙煎し、その後、ブレンドする管理システムを開発。
産地品質の最適化焙煎を目的とした。
当時、他メーカーでは、コーヒー生豆を先にブレンドして焙煎する方法=先ブレンド方式。
産地の特徴は、標高と緯度(コーヒー生産ベルト地域19度内)は、品種、豆の粒度、味のコク、酸味・苦味・香り、特徴が異なる。コーヒー焙煎機械はドイツ製が主流、ドイツの焙煎メーカーは世界各地の上質品を焙煎・冷却の技能を高めていた時代。
|
| 1992年 |
千葉漁連入札権取得 |
| 1994年 |
- スリランカに鮮度保持ブレンド施設を設立
- 熱帯気候であるスリランカに、鮮度保持のため、紅茶ブレンド施設を設立。また、アルミ真空包装機を設置。
紅茶茶葉のリーファーコンテナ輸入開始。管理システムを開発。
- コーヒー事業に参入
- コーヒーの需要大国、北欧の市場を調査。
200g缶入りのレギュラーコーヒーが3缶で¥1,000の販促が主流のとき、レギュラーコー
ヒーの需要拡大予測と消費者のコスト削減のために、日本のコーヒー業界に先駆けて、袋
詰めレギュラーコーヒー(粉)お徳用500gを¥498の価格で発売。このとき、日経夕刊
に掲載されているコーヒー相場をもとに、輸入諸経費を一覧化して、バイヤーに商品の原
価と品質価値を説明できる商談で信頼を勝ち取る。

- お徳用ドリップコーヒー開発
- 個食化対応の一杯用ドリップコーヒーのおいしさUP、8g商品発売。
他社は内容量6gで、6Pタイプが主流であったが、お徳用の10Pタイプを自動包装にてコストダウンして、
買い易い価格で発売。イトーヨーカドー様、ならびに当時のジャスコ様全店で定番化。
- お徳用ペーパーフィルター開発業界初
- レギュラーコーヒーの家庭内チャンスロスの改善に、コーヒーフィルター120枚をイギリス
のフィルターメーカーで開発して直輸入。他社が40枚入りで¥98で販売している中で、3倍
の120枚入りで、価格は2倍の¥198で発売開始。

|
| 1995年 |
1月静岡工場を6F建てに増築、内、包装フロアー(163坪×4フロアー) 他、出荷場・事務所160坪 |
| 1996年 |
喫茶事業カフェ・レント店、アバンス店 テスト業態開始 |
| 1997年 |
- クニタロウオーストラリアPTY LTD設立 資本金60万豪ドル
- オーストラリアでの茶事業の本格化。緑茶の有機農園開発に向けて、日本茶の苗木をオーストラリアへ輸出開始。NSW州農務省の研究施設で、緑茶栽培共同研究開始。
|
| 1998年 |
- 有機麦茶開発業界初
- オーストラリアNSW州ゴスフォードに、有機大麦の契約栽培を開始。また、焙煎包装工場落成。
日本に有機認証制度がない時に、オーストラリアの有機認証機関BFAの認証で、有機栽培麦茶を開発。
イトーヨーカドー様(2001年)、ジャスコ様(2002年)、みやぎ生協様(1999年)にてPB商品化。
静岡工場・理科学研究室設置(茶成分分析と原料撰定基準)し、オリジナル、OEM強化
|
| 1999年 |
HACCPシステムによる総合衛生管理手法(食品の安全性を確保)取組開始 |
| 2001年 |
- 増資 資本金18,000万円・JAS(有機麦茶等)認定工場となる
- 販売促進情報発信センター建設(情報を一元管理 開設・本社機能業務開始)
|
| 2002年 |
厚木・千葉営業所、情報センターへ統合 |
| 2003年 |
- 海苔火入れ伸ばし機導入
- 初網みの風味豊かな新海苔を、マイナス20度の冷凍庫で保管。
従来は180分で火入れ伸ばしを行っており、酸素に触れる時間が長い為、風味が酸化していた。
これを7分間で火入れ伸ばし、その後、焼き釜に直結させて、旨味と風味を閉じ込めた、価値
ある焼のり重等級の発売。
包装フィルムもアルミに近い保持性の資材を使用して、乾燥剤と脱酸素剤を入れて品質保持。
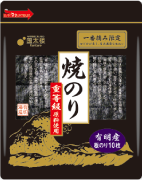
- 海苔ラインHACCP認証取得
- 静岡工場(海苔生産フロア)が、HACCP推進協議会、および財団法人東京顕微鏡院によるダブル認定。
- JAS(有機紅茶・有機コーヒー)認定工場となる。
- HACCP推進協議会・財団法人東京顕微鏡院ダブル認定工場となる。
|
![]() 国太楼の歴史
国太楼の歴史